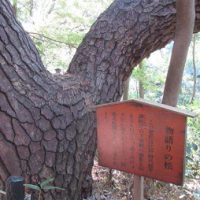関東
【秋】子規庵吟行記
室内の佇まいを拝見後、子規の云う「小園」を巡る。軒先の棚には14、5本の糸瓜が下がり、小径に石蕗の花、杜鵑草など句題に事欠かない。この時期、むしろ花の種類の多さに驚かされた。これもボランティァの方々の影の力によるものだろうか。
【夏】秋川渓谷吟行記
JR武蔵五日市駅より、車で10分。秋川渓谷沿いの古刹「広徳寺」へ。境内は鬱蒼とした木々に包まれ、老鶯の声に迎えられる。境内散策後、バスで奥多摩入口の岩瀬峡へと移動。ここでせせらぎの音に混じって河鹿の鳴き声を存分に聴くことが出来た。
【春】絹の道吟行
八王子市の東南部多摩丘陵の一角に位置する「絹の道」の吟行した。地名の由来は、幕末から明治にかけて隆盛を極めた生糸貿易の荷駄が、横浜へ向けこの道を頻繁に往来したことからきている。
【新年】浜離宮庭園『放鷹術の実演』等吟行記
放鷹術は野外スポーツとして貴人に好まれ、古くは仁徳、一条などの諸天皇や家持、家康など熱心な愛好者の支援があったが、戦後は諸般の事情により政府による鷹狩は行われなくなり放鷹術は民間の有志に受け継がれ今日に至っているとのこと。
【冬】自然教育園吟行記
自然教育園の歴史は室町時代の豪族の館から始まり、江戸時代は徳川光圀の兄にあたる高松藩松平頼重の下屋敷、明治時代は陸海軍の火薬庫、大正時代には白金御料地になっている。この間、一般人は立ち入ることが出来なかったため都心ではまれに見る豊かな自然が残されている。広さは東京ドーム四つ分である。
【秋】府中大國魂神社・東京競馬場吟行記
大國魂神社は出雲の大國主神と御同神の大國魂大神を護り神として祀った武蔵野国の総社で、創建は凡そ1900年前の西暦111年5月5日である。六所の宮を合祀しているところから六所宮とも呼ばれている。毎年創建の5月5日を中心に例大祭が催されるが、通称「くらやみ祭」として広く知られている。
【秋】菊坂吟行記
まず樋口一葉終焉の地、本郷丸山福山町。そこで2年6カ月の間に名作「おほつごもり」「たけくらべ」「にごりえ」「十三夜」などを生みました。菊坂を登り始めるとすぐに「伊勢屋」という一葉がしばしば通ったと言われる質屋がほぼ当時のままに残されています。一葉の旧居の跡には当時のポンプ井戸も残っています。
【夏】府中郷土の森博物館吟行
まず江戸時代から昭和初期にかけての市内にあった建物を移築・復元されたゾーンを見学。自然豊かな園内には、今まさに竹皮を脱いでいる竹林、刈り取る寸前の麦畑、代搔きを終えた田んぼ、まだ蕾の紫陽花の傍では水車小屋を見学。七千万年前の樹木化石の珪化木や、縄文時代の遺跡、まいまいづ井戸など古代に思いを馳せるなど、盛り沢山の散策でした。
花祭吟行(4月8日)
丁度花祭の日と重なり、午前中花祭のお寺を吟行することになりました。あきる野市の東秋留地区のお寺では「花まつりオリエンテンプリング」と銘打って八つのお寺巡りの催しがあり今年が30回目だそうです。今回は、その中のJR東秋留駅付近の三つのお寺としました。
【春】両国周辺吟行
はじめに隅田川の河畔散策路へ。次いで回向院へ。回向院から吉良邸跡へ向かう。次に本日のメインの「すみだ葛飾北斎美術館」へ。富岳三十六景をはじめ北斎の風景の緻密で繊細な絵、そして一方で大首絵などの大胆な構図の作品などをじっくり鑑賞。
【春】あきる野周辺吟行
五日市線「武蔵引田」駅に集合。駅舎では燕が巣作りを開始。咲き初めた桜の巨木の上空を飛翔している。南方には多摩川を挟み「多摩横山の丘陵」を、西には「奥多摩の連山」を望む長閑な里山である。
【冬】世田谷ぼろ市
先ず井伊家一族の眠る豪徳寺に向かう。次に吉良家の居城であった世田谷城址公園に歩を進める。さて本命のぼろ市が開かれる世田谷は、小田原と江戸を結ぶ宿駅として栄え、小田原城主北条氏政が市場税を免除して行商販売を認めた。ごった返しのぼろ市をやっと抜け出し、松陰神社へ。